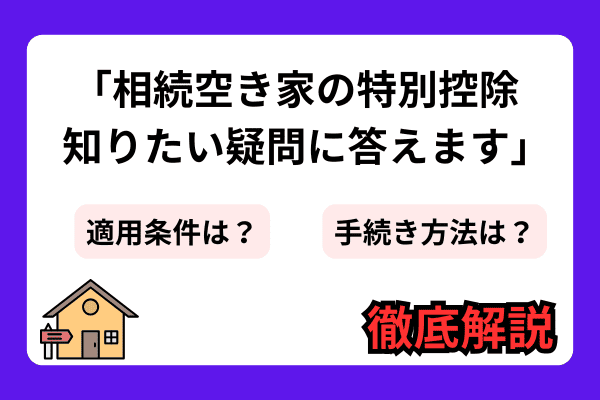- 相続空き家の特別控除ってなに?
- 受けるための条件は?
- どれくらい得できるのか教えて!
『相続空き家の特別控除』とは、相続した空き家を売って利益を得た際、最大3,000万円控除できる制度です。
しかし、誰もが知っている一般的な制度ではないため、疑問や不安を抱いている方も多いでしょう。





【こんな人に読んでほしい】
- 相続空き家の処分に困っている
- 売るときの税金を安くしたい
- 特例を受けたいけど、よくわからない
「相続空き家の特別控除 知りたい疑問に答えます」とは
「相続空き家の特別控除 知りたい疑問に答えます」とは、日本経済新聞が公表している「相続空き家の特別控除」に関する記事です。
『相続空き家の特別控除』の概要や適用条件などを専門家が詳しく解説しています。また、よくある疑問に対しても回答しており、特別控除を受けようとしている方にとって役立つ情報を発信しています。
相続空き家の特別控除の利用を検討している方は、一度読んでみましょう。
相続空き家の特別控除とは?基本をわかりやすく解説
「相続空き家の特別控除」とは、相続した空き家を売るとき、最大3,000万円まで利益が非課税になる制度のことです。
対象になるには、親が一人暮らしだった家であること、築年数が古い木造住宅であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、耐震改修済みであるか、更地にして売ることも条件に含まれます。
例えば、2,500万円で取得した家を3,800万円で売った場合、以下の計算式になります。
「3,800万円(売却額)-2,500万円(取得費)=1,300万円」
譲渡所得は1,300万円となり、ここに譲渡所得税がかかります。しかし、相続空き家の特別控除を使えば、譲渡益1,300万円が非課税になります。
期限は相続から3年目の年末まで。税金を大きく減らせるチャンスなので、売却前に条件をよく確認しておきましょう。
譲渡所得とは?控除とセットで知っておきたい基礎知識
譲渡所得とは、売った価格から取得費や経費などを差し引いて残る利益のことです。
相続空き家で例えると、親の家を2,000万円で売り、取得費や経費が800万円だった場合、差額の1,200万円が譲渡所得になります。
この金額に対して税金がかかりますが、「相続空き家の特別控除」を使えば最大3,000万円まで利益が差し引かれます。売却益が3,000万円以内なら、税金がかからない場合もあります。
制度を使うには、相続からの期間や家の状態など一定の条件を満たす必要があります。正しく申告すれば大きな節税につながります。
【3つの条件】相続空き家の特別控除を受けられるかチェック
相続空き家の特別控除を受ける前に以下3つのポイントをチェックしておきましょう。
- どんな人が対象になるか
- いつまでに売却すればいいか
- 相続後の使い方に注意
どんな人が対象になるか
相続空き家の特別控除を受けるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 相続で取得した一戸建てを売る予定の人
- 被相続人(亡くなった人)が一人で住んでいた
- 売却時までに空き家で、誰も住んでいない状態
- 売却価格が1億円以下
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅で、必要に応じて耐震工事を行っている
参照:国税庁「特例の適用を受けるための要件」
例えば、親が一人で住んでいた実家を相続し、そこに誰も住まずに売却するケースでは対象になる可能性があります。
逆に、兄弟などと共有で相続したり、すでに賃貸に出したりしていると使えないことがあります。条件をひとつずつ確認しましょう。
いつまでに売却すればいいか
相続空き家の特別控除を受けるには、売却のタイミングがとても重要です。期限を過ぎると控除が使えなくなる可能性があります。
例えば、2023年に相続が完了した場合、2026年12月31日までに売却契約を結ぶ必要があります。つまり、相続した年の翌年1月1日から3年以内の年末までが目安です。
売却期限のポイントは以下のとおりです。
相続が完了した年の翌年の1月1日が起算日
そこから3年が経過する年の12月31日までに売却すること
売買契約が成立していれば年内に引き渡さなくても対象になる
売却を先延ばしにすると思わぬ出費につながるかもしれません。特別控除を無駄にしないためにも早めに準備を始めましょう。
相続後の使い方に注意
相続した家を売って特別控除を使いたい場合、相続後の使い方に注意が必要です。
例えば、売却前に他人に貸したり自分で住んだりすると、特別控除が使えなくなるケースがあります。
国の制度では「相続後は誰も住んでいない状態」が条件の一つとされているためです。たとえ短期間でも使用すると対象外になる可能性があるため、売却前に活用予定があるなら慎重な判断が求められます。
築年数や構造で変わる?対象住宅の見分け方
相続空き家の特別控除は、住宅の築年数や構造によって受けられるかどうか異なります。
相続空き家が以下の条件を満たしているか確認しておきましょう。
- 昭和56年5月31日以前に建てられたか
- 木造かどうかをチェック
- 耐震性があるかどうかも確認
昭和56年5月31日以前に建てられたか
相続空き家の特別控除を受けるには、家の築年数が重要なポイントです。
対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた古い家が中心とされています。これは昔の建築基準に基づいて建てられているためで、現在の耐震基準を満たしていない可能性があると見なされやすいからです。
自宅の「建築年月」は、登記簿謄本や固定資産税の明細書などで確認できます。昭和56年6月以降に建てられた家は、この控除の対象にならないケースがあるため注意が必要です。
ただし、条件に合うかどうかは建物の構造や使用状況も関係します。売却前に不動産会社や税理士に相談すると安心です。
木造かどうかをチェック
相続空き家の特別控除を受けるには、「木造かどうか」の確認が重要です。
対象になるのは、被相続人が一人で住んでいた戸建てで、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が基本です。この築年数の基準は、当時の耐震基準をもとに決められています。
ただし、非木造の建物やマンションは対象外となることが多いため注意が必要です。また、旧耐震基準の木造住宅でも、耐震リフォームを行えば対象になるケースがあります。
建物の構造は登記簿で確認できますが、不安な場合は不動産会社に相談すると安心です。見た目だけでは構造は判断できないため、事前確認が欠かせません。
耐震性があるかどうかも確認
相続空き家の特別控除を受けるには、築年数や構造だけでなく、耐震性も確認が必要です。
特に1981年6月より前に建てられた住宅は、旧い基準で建てられている場合があります。耐震性が確認できなければ控除対象にならない可能性があるため、注意が必要です。
例えば、木造の一戸建てで1980年築の場合、そのままでは適用が難しいケースも見られます。ただし、リフォームなどで現行基準を満たしていると証明できれば対象になることもあります。
確認には自治体や建築士による診断が役立ちます。控除を受けたい方は、売却前に耐震診断を行い、証明書を取得しておくと安心です。
対象になるかどうかを判断するためにも、建物の状態を正しく把握しておきましょう。
確定申告で必要な書類は?手続きの流れを4ステップで解説
相続空き家の特別控除を受けるには、確定申告が必要です。
以下のステップを踏んで確定申告を進めましょう。
- 登記簿や売買契約書を用意
- 「被相続人居住用家屋等確認書」の取得
- 申告書類の作成
- 税務署への提出
STEP①:登記簿や売買契約書を用意
まず登記簿や売買契約書などの書類を揃えましょう。これらは、家の名義や売った事実を証明する重要な資料です。
登記簿は法務局で取得でき、売買契約書は不動産会社を通じて入手した書類を使います。もし書類を紛失していても、法務局や関係先に確認すれば再発行が可能な場合もあります。
確定申告の場では原本ではなくコピーで構いませんが、内容に不備があると控除を受けられなくなる恐れがあります。
築年数や構造など家の詳細がわかる資料も一緒に準備しておくと安心です。
STEP②:「被相続人居住用家屋等確認書」の取得
「被相続人居住用家屋等確認書」とは、亡くなった人が一人で住んでいた家だったと証明する書類です。市区町村に申請して発行してもらいます。
住民票の除票や名寄帳など、役所が求める資料をそろえる必要があります。提出先や必要な書類は自治体によって違う場合があるため、事前に電話などで確認しておくと安心です。
取得には日数がかかることもあるため、売却前に早めに動くことをおすすめします。
STEP③:申告書類の作成
申告書類の作成では、まず売却で出た利益をまとめ、税務署に提出する書類を整えます。利益が出たかどうかは「売った金額」と「取得時の費用+売却時の費用」で計算されます。
利益が出ていれば、相続空き家の特別控除を使って最大3,000万円まで非課税にできます。必要な書類には、売買契約書、登記簿、取得費のわかる資料、被相続人が住んでいた証明、確認書などがあります。
これらをもとに譲渡所得の計算を行い、確定申告書を作成します。不安がある場合は、税理士や税務署で確認しながら進めると安心です。
STEP④:税務署への提出
最後に、作成した申告書類を税務署へ提出しましょう。提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。
売却翌年の2月16日~3月15日が基本期間ですが、早めの準備が安心です。提出には申告書Bや譲渡所得の明細書、売買契約書のコピー、登記事項証明書、戸籍謄本などが必要です。
被相続人が一人暮らしだった証明書類も添える必要があります。郵送やe-Taxでも提出できますが、不備があると再提出になることもあります。
提出前に不動産会社や税理士に確認しておくと安心です。
特別控除でいくら節税できる?簡単シミュレーション例
相続空き家の特別控除を活用したシミュレーションを解説します。例えば、親の持ち家を相続し、2,500万円で売れたとします。取得時の価格は500万円、売るためにかかった費用が100万円だった場合、次のように計算されます。
【譲渡益の計算式】
売却価格 − 取得価格 − 費用 = 利益(譲渡益)
2,500万円 − 500万円 − 100万円 = 1,900万円
この1,900万円に対して、3,000万円の控除が適用されると利益が0円とみなされます。結果として、所得税や住民税がかからないケースもあります。
ただし、控除が使えるかどうかには条件があります。家が古いかどうか、相続後に誰も住んでいなかったかなどの確認が必要です。
控除が使えれば、税額が数十万円から数百万円減る可能性もあります。売却前に税務署や不動産会社に確認しておくと安心です。
他の控除や特例と併用できる?注意すべきポイント
相続空き家の特別控除は、ほかの控除と併用できる場合があります。
併用できる特例と併用できない特例を理解しておきましょう。
- 居住用3000万円控除との違い
- 併用できる特例とできない特例
- 同時申請できない場合の注意点
居住用3000万円控除との違い
相続した空き家を売るとき、「相続空き家の特別控除」と「居住用3000万円控除」の違いを理解しておくと、税金の負担を減らせます。
どちらも譲渡所得から最大3,000万円を引ける制度ですが、使える場面が異なります。相続空き家の特別控除は、亡くなった親などが住んでいた家を売るときに使える制度で、一定の条件を満たせば、住んでいなくても対象になります。
一方、「居住用3000万円控除」は、自分が住んでいた家を売るときに使います。例えば、親が住んでいた家を相続して売る場合、自分が住んでいなくても「相続空き家の特別控除」の対象になる可能性があります。
ただし、耐震性や空き家期間などの条件があるため、確認が必要です。両方の制度は併用できないため、どちらが適用されるかを事前に確認するのが安心です。
併用できる特例とできない特例
相続空き家の特別控除と併用できる特例と、できない特例を以下の表にまとめました。
| 特例・控除の名称 | 併用の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円控除 | × | 自分で住んでいた家に使える制度で、相続空き家とは使い分けが必要です。 |
| 特定居住用財産の買換え特例 | × | 家を買い替えるときの税優遇ですが、相続した家には当てはまりません。 |
| 譲渡損失の損益通算と繰越控除(居住用) | × | 売って損をした場合に使う制度で、利益を減らす相続空き家の特例とは併用できません。 |
| 空き家対策特例(最大3,000万円控除) | ○ | 今回の相続空き家の制度にあたります。他の空き家特例と混同しないよう注意が必要です。 |
| 配偶者控除(相続税) | ○ | 相続時に使うもので、売却時の税金とは別の制度です。併用できます。 |
| 小規模宅地等の特例(相続税) | ○ | これも相続時の評価を下げるもので、売却時とは関係なく使えます。 |
【注意したいポイント】
- 同じ「3,000万円控除」でも種類が違うため、間違えないようにしましょう。
- 売却の利益が出ない場合は、あえて申請しないこともあります。
- 制度の条件は細かく、税務署や専門家に確認するのが安心です。
同時申請できない場合の注意点
相続空き家の特別控除は、他の控除や特例と重ねて使えない場合があります。
例えば、「居住用財産の3,000万円控除」や「譲渡損失の損益通算」との併用が制限されるケースがあります。控除を確実に使いたいなら、税理士や不動産会社に早めに相談しておくと安心です。
また、確定申告では必要書類の提出順や申告内容が重ならないよう整理が必要です。売却価格が高くなりそうな場合は、どの特例を選ぶと負担が少ないかを試算しておくとよいでしょう。
例えば、2,500万円で売却する場合、「相続空き家の特別控除」の3,000万円を使えば課税対象をゼロにできますが、他の控除を同時に申請しようとすると却下される可能性もあります。
制度の併用条件を知らずに進めると、控除が使えず思わぬ税金が発生するリスクもあるため注意が必要です。
売却前に確認!不動産会社との相談ポイント
相続空き家の売却について、不動産会社へ相談する際は以下のポイントを押さえましょう。
- 査定だけでも頼める?
- 空き家売却に強い会社の見分け方
- 仲介と買取、どちらが向いている?
査定だけでも頼める?
査定だけでも依頼できます。不動産会社に相談したからといって、必ず売らなければいけないわけではありません。
相続した空き家の価値を知っておくと、売却するかどうか判断しやすくなります。実際、多くの人が「まず査定だけ」と気軽に依頼しています。
訪問してもらうのが不安なら、机上査定という書類だけで判断する方法もあります。もちろん、その後の営業連絡が気になる場合は、最初に「今回は査定だけお願いします」と伝えておくと安心です。
費用は無料のケースがほとんどなので、悩む前に一度相談してみるのも選択肢です。
空き家売却に強い会社の見分け方
空き家の売却を成功させるには、空き家に強い不動産会社を選ぶことが近道です。
相続後の空き家は管理の手間や税金負担があり、早めの売却が求められます。ただ、すべての会社が空き家の扱いに慣れているわけではありません。選ぶときは「空き家の売却実績があるか」「相続相談に対応しているか」をチェックしましょう。
例えば、「空き家専門ページ」や「税金のサポートがある」といった情報がある会社は頼りになります。また、成約までの平均日数や査定の根拠も確認しておくと安心です。
話を聞いたうえで複数社を比べると、相性の良い担当者も見つけやすくなります。
仲介と買取、どちらが向いている?
相続空き家の売却では「仲介」と「買取」のどちらが合うか、状況に応じた見極めが大切です。
- 時間に余裕がある、少しでも高く売りたい:仲介
- 早く現金化したい、遠方で管理が難しい:買取
仲介では売却までに数ヶ月かかることもありますが、相場より高く売れる可能性もあります。買取は価格が抑えられる傾向がある反面、手間が少なくスムーズに終わる点が魅力です。
不動産会社に相談する際は、両方のメリットと注意点を確認し、自分の希望に近い方法を一緒に考えてもらいましょう。
相続空き家の特別控除に関するよくある質問3選
相続空き家の特別控除に関するよくある質問をご紹介します。
特別控除を受ける方は参考にしてみましょう。
- 売却期限を過ぎたらどうなる?
- 取り壊した家でも対象になる?
- 住民票の移動は必要?
Q:売却期限を過ぎたらどうなる?
A:相続空き家の特別控除は、期限を過ぎると使えなくなります。
控除を使えるのは、相続から3年目の年末までに売却契約を結び、翌年2月15日までに申告を済ませた場合です。
例えば、2021年に相続した家なら、2024年12月31日までに契約しなければ対象外になります。期限を過ぎても売却は可能ですが、3,000万円の控除は受けられなくなります。
予定よりも売却が長引きそうなときは、不動産会社に早めに相談し、スケジュールを見直しましょう。
Q:取り壊した家でも対象になる?
A:取り壊した家でも特別控除の対象になる可能性はあります。
一定の条件を満たせば、家が取り壊されていても控除を受けられる制度になっています。
例えば、売却時に家が存在していない場合でも、「被相続人が住んでいた」「取り壊し後すぐに売却した」「売却まで誰も使っていない」などの条件をクリアしていれば対象になります。
申請には、解体した時期や売却までの状況を証明できる書類が必要になるため、登記簿や解体業者の契約書、売買契約書などを手元にそろえておくと安心です。不安な場合は、税務署や不動産会社に事前確認することをおすすめします。
Q:住民票の移動は必要?
A:住民票の移動は基本的に必要ありません。
条件を満たせば、故人が住んでいた家を相続した人が遠方に住んでいても適用できます。ただし、相続後に誰かが住んでいた場合や、空き家としての状態が続いていない場合は対象外になることがあります。
例えば、相続後に別の家族が住んでいたケースや、賃貸に出していた場合などが該当します。
控除を受けるには、一定の期間内に売却し、耐震性や建物の種類にも注意が必要です。
まとめ:相続空き家の特別控除の制度を理解して税金を安くしよう!
相続空き家の特別控除を上手く活用することで、相続空き家を売った際の税金を安く抑えられます。
最大で3,000万円分を控除できるため、譲渡所得額によっては税金を0にできるケースもあります。
ただし、利用するにはいくつかの条件を満たす必要があり、誰でも利用できるわけではありません。また、利用するには確定申告も必要となり、手間や時間も多少かかります。
それでも、特例を利用できれば非常に大きな節税につながるため、相続空き家の売却を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして手続きを進めてみましょう!
「相続」に関する記事一覧はこちら!