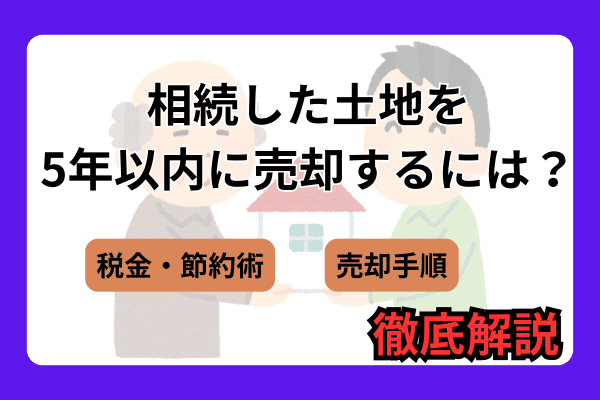- 土地を相続したけど使わないから売りたい……。
- 相続後の手続きってどうすればいいの?
- 売るまでの流れを教えて!
土地を相続した場合、相続人が所有者となるため、土地を利用していなくても固定資産税などの税金が発生します。
そのため、「早く売却したい」と考える方も多いでしょう。しかし、相続不動産を早く売却しようとすると思わぬトラブルに発展する可能性があります。





【こんな人に読んでほしい】
- 相続した土地の処分に困っている
- 土地を売却する際の税金を抑えたい
- そもそも土地売却が初めてで不安
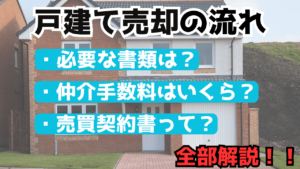
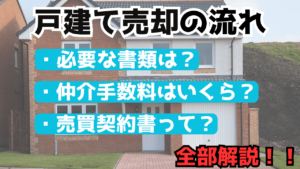
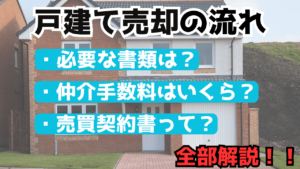
相続した土地を5年以内に売却するなら税金に注意
相続した土地を5年以内に売却するなら、税金に注意しましょう。土地を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかります。
【譲渡所得税とは】
不動産を売った際の利益に対して課される税金
例えば、当時2,000万円で買った不動産を3,000万円で売却した場合、1,000万円が利益(譲渡所得)となり、ここに譲渡所得税がかかります。




税率は、不動産の所有期間により以下のように異なります。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 所得税:30% 住民税:9% 復興特別所得税:所得税額の2.1% 合計:39.63% |
| 5年超え | 所得税:15% 住民税:5% 復興特別所得税:所得税額の2.1% 合計:20.315% |
所有期間が5年以下なら約39%、5年を超えると約20%と大きく変わります。
ただし相続の場合、所有期間は故人が土地を取得した日から計算されます。たとえば、20年前に父が買った土地を相続してすぐ売った場合でも、長期保有と見なされる可能性があります。




また、取得費がわからないと税額が高くなるおそれもあります。売却前に税理士など専門家に確認すると安心です。
相続した土地を売却した際にかかる税金の種類
相続した土地を売却した際は以下の税金がかかる場合があります。
- 譲渡所得税
- 住民税
- 登録免許税
- 印紙税
譲渡所得税
相続した土地を売ると、譲渡所得税がかかる場合があります。
前述のとおり、売却額から購入時の価格や諸費用を引いて利益が出たときに発生します。
相続の場合は、亡くなった方の購入時の価格を引き継ぎます。たとえば、20年前に500万円で買った土地を2,000万円で売ると、1,500万円が課税対象です。




相続では元の所有期間も引き継がれるため、多くは「長期譲渡」となり、約20%の税率が適用されます。短期の場合は約39%です。
特別控除を使えば、納める税金を減らせる可能性もあります。具体的な計算は専門家に相談しましょう。
詳しくは、国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」をご覧ください。
住民税
相続した土地を売り、譲渡所得(利益)が発生すれば、住民税もかかります。
住民税は基本的に約5%かかります。たとえば500万円の譲渡所得が出た場合、住民税はおよそ25万円です。
ただし、相続後の使われ方や売却時期によっては、特例や控除が使える場合もあります。条件を満たせば税金を抑えられる可能性があるため、申告前に確認しておきましょう。




登録免許税
相続した土地を売るには、まず名義を自分に変える手続きが必要です。このときにかかるのが「登録免許税」です。
亡くなった人の名義から相続人の名前へ変更する際に発生し、目安は「土地の評価額×0.4%」です。たとえば評価額が1,000万円なら、「1,000万円×0.4%=4万円」となります。
登記の前に払う必要があり、それ以外にも手続きを司法書士に頼むと報酬がかかります。金額は大きくありませんが、売却前に必要な費用として見落とさないようにしましょう。
詳しくは、国税庁「登録免許税の税額表」をご覧ください。
印紙税
土地を売るときは、売買契約書に「印紙税」がかかります。これは国に納める税金で、契約金額によって金額が決まります。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
引用:国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
たとえば売却額が1,000万円を超えて5,000万円以下なら1万円かかります。
支払い方法は、印紙を契約書に貼り、押印すれば納税完了です。貼り忘れた場合、税務署から指摘されて本来の税額に加え、最大3倍の過怠税が課されることがあります。
契約書は売主・買主が1通ずつ持つことが多く、それぞれが印紙代を負担します。土地を売る際の費用として、忘れずに準備しておきましょう。
相続した土地を売却した際に利用できる控除特例
相続した土地を売却した際、以下の控除特例を利用できるケースがあります。
- 3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
- 相続した農地の納税猶予制度
3,000万円特別控除
相続した家付きの土地を売却する場合、「3,000万円の特別控除」が使えると税金を大きく減らせます。
【3,000万円特別控除とは】
マイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度
この控除は、被相続人が一人で住んでいた家を相続し、その後誰も住まずに、建物を取り壊して一定の期間内に売却した場合に使えます。




たとえば2023年に相続したなら、2026年12月31日までに売る必要があります。条件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円を差し引けるため、税負担が軽くなります。
ただし、細かい要件が多く、誤ると適用されません。売却を考えているなら、早めに税理士や不動産会社に相談して準備を進めましょう。
取得費加算の特例
相続した土地を売るなら、「取得費加算の特例」を検討しましょう。
【取得費加算の特例とは】
相続税を支払っていれば、その一部を土地の取得費に加えられる制度
たとえば、3,000万円で土地を売り、取得費が1,000万円、相続税が600万円だった場合、取得費は1,600万円になります。
通常であれば、取得費1,000万円分しか差し引けないですが、この特例を利用することで相続税も取得費に加算でき、差し引ける金額を大きくできます。
その結果、譲渡所得を少なくでき、課される税額も少なくできるのです。
ただし、この特例は相続があった年から3年以内の年末までに売却するなどの条件があります。土地を売るときは、税金対策としても有効なので、使えるかどうかは早めに税理士に相談しましょう。
詳しくは、国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をご覧ください。
相続した農地の納税猶予制度
相続した農地は、農業を続ける人に限って相続税の納税を先延ばしにできる「納税猶予」の制度があります。
これは、親から農地を引き継ぎ、自ら農業を行うときに利用できます。条件を満たせば相続税の支払いが猶予され、将来的に免除されることもあります。




ただし、農業をやめたり農地を売却したりすると、猶予されていた税金を一括で支払う必要があります。たとえば評価額3,000万円の農地なら、条件によっては数百万円の税負担になることもあります。
売却を検討する場合は、農地のまま売れるか、税金の扱いはどうなるかを確認しましょう。農業委員会や税理士に相談してから判断するのがおすすめです。
詳しくは、国税庁「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」をご覧ください。
相続した土地を5年以内に売却する際の流れ・必要な準備
相続した土地を5年以内に売却するなら、以下の流れで売却を進める必要があります。
- 法務局で名義変更の手続き
- 土地の場所や広さなどの現地調査
- 近隣の売却実績を調べて相場の把握
- 不動産会社へ依頼
- 測量・境界確認
- 買い手と売買契約
- 決済・引き渡し
STEP①:法務局で名義変更の手続き
まず名義を自分に変える手続きが必要です。名義が故人のままだと売買契約できないためです。
名義変更は法務局で行いますが、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 土地の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続人全員の戸籍や関係が分かる書類
これらを事前に揃えましょう。名義変更は専門家に依頼できますが、数万~10万円ほどかかります。
申請してから1~2週間程度で名義が変わります。名義変更が遅れると売却時期もずれやすくなるため、相続後はできるだけ早く動きましょう。




詳しくは、法務局「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください。
STEP②:土地の場所や広さなどの現地調査
名義変更が完了したら、現地調査をしましょう。
【調査内容】
- 土地の場所
- 土地の広さ
- 土地の形
- 土地に接している道路の幅
間口が狭い土地や、前の道路が狭いと家が建てにくくなり、買い手が見つかりにくくなることもあります。また、土地の一部が傾いていると、建物を建てる際に追加の工事費がかかるため、購入をためらわれる場合もあります。




また、登記上の面積と実際の広さが合っているか、土地の境界を示す杭があるかも見ておきましょう。
不動産会社に相談すれば、こうした調査を代わりに進めてくれるため、不安な方は相談してみてください。
STEP③:近隣の売却実績を調べて相場の把握
次に、近隣の取引事例を調べて相場をつかみましょう。売却価格の目安を知ることで、買い手に納得してもらいやすくなります。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、地域や時期を指定して実際の売買価格を調べられます。たとえば、世田谷区で100㎡の土地が8,100万円で取引された例も確認できます。




また、「SUUMO」や「ホームズ」などの不動産ポータルサイトでは、今売り出されている似た土地の情報も参考になります。
ただし、売出価格は実際の売却価格より高めな傾向があるため注意しましょう。条件の近い土地と比べて、無理のない価格を設定することが成功のポイントです。
STEP④:不動産会社へ依頼
相場をつかんだら、不動産会社に売却を依頼しましょう。信頼できる会社を選ぶことで、手続きがスムーズに進みやすくなります。
不動産会社を選ぶ際、まずは複数の会社に無料査定をお願いし、説明がわかりやすく丁寧かを確認しましょう。査定額だけでなく、広告の出し方や販売戦略も比較してください。




また、「早く売りたい」と「高く売りたい」では、適した会社が異なる場合があります。対応エリアや過去の売却実績も見ておくと安心です。
STEP⑤:測量・境界確認
不動産会社へ相談したら、測量と境界確認を行いましょう。境界があいまいな土地は買主に不安を与えるため、トラブルを防ぐためにも重要です。
専門の測量士に依頼して、土地の広さや隣地との境界を明確にしましょう。費用の目安は20万~40万円ほどですが、確定測量を選ぶとより正確です。
また、隣地の方に立ち会ってもらう必要がある場合もあり、日程調整に時間がかかることがあります。測量図があれば登記や売買契約がスムーズに進み、土地の評価にも良い影響があります。
売却を検討し始めたら、できるだけ早めに準備を始めましょう。
STEP⑥:買い手と売買契約
売却活動により買い手が見つかったら、売買契約の準備を進めましょう。
売買契約の前に、価格や引き渡し時期、支払い方法などを買い手としっかり確認します。口約束では後でトラブルになる可能性があるため、不動産会社を通して正式な契約書を交わすのが一般的です。




売買契約時、売主は以下の書類を用意します。
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 登記識別情報
- 固定資産税の通知書
すべての書類を揃えるのに時間がかかる可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。
また、契約時には買主から手付金(物件価格の5~10%)を受け取ります。契約が済めば、いよいよ決済と引き渡しの準備です。内容をよく理解しながら、慎重に進めましょう。
STEP⑦:決済・引き渡し
売買契約後は、買主から代金を受け取り、土地を正式に引き渡します。
一般的に決済の場には司法書士が同席し、代金の入金を確認してから所有権移転の登記申請を行います。このときに、固定資産税の精算や仲介手数料の支払いも済ませましょう。
相続した土地を売る場合は、相続登記が終わっていないと登記手続きができないため、必ず事前に済ませておく必要があります。
当日は、実印や本人確認書類を忘れずに持参しましょう。安心して引き渡すためにも、あらかじめ不動産会社や司法書士と流れを打ち合わせしておくのがおすすめです。
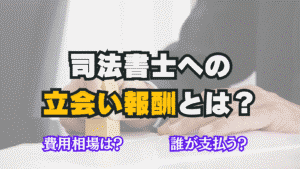
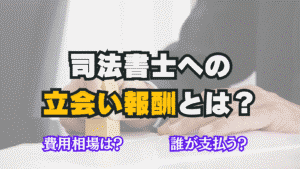
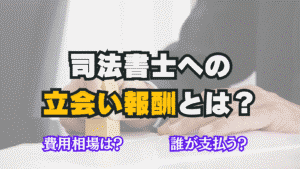
確定申告は必要?相続した土地を売却したときの手続き方法
相続した土地を売却した場合、利益が出ると確定申告が必要です。
売った金額が、相続前に所有していた人の購入価格より高ければ、その差額が利益として扱われます。
譲渡所得については、国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」をご覧ください。
なお、税金がかかるかどうかを判断するには、相続した日や売却額、取得費などをもとに計算しましょう。
売却が決まったら、売買契約書や登記簿のコピー、相続を証明する書類などを準備しておくと安心です。不安な点があるときは、税務署や税理士に早めに相談しましょう。
準備を早めに進めることで、手続きがスムーズになります。
相続した土地を5年以内に売却するうえで知っておくべき3つのポイント
相続した土地を5年以内に売却する際は、以下3つのポイントを理解しておきましょう。
- 譲渡所得と譲渡損失のどちらか
- 相続登記をすませておく
- 特例の対象になるか調べる
譲渡所得と譲渡損失のどちらか
相続した土地を売るときは、「利益が出るか損になるか」で税金の扱いが変わります。前述のとおり、利益が出れば「譲渡所得」として確定申告が必要です。
一方、譲渡損失の場合は所得を得ていないので確定申告は不要です。
なお、譲渡所得において注意したいのは「所有期間の計算」です。売却した土地の所有期間が、5年を超えているか超えていないかで税率が約2倍も異なります。
| 不動産の所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下 | 所得税:30% 住民税:9% 復興特別所得税:所得税額の2.1% 合計:39.63% |
| 5年超え | 所得税:15% 住民税:5% 復興特別所得税:所得税額の2.1% 合計:20.315% |
5年を超えていないと約40%、5年を超えている場合は約20%の税率で済みます。
しかし、相続不動産の場合は、自分が取得した日ではなく、もともとの所有者が買った日が起点になります。




そのため、相続から5年以内でも「長期」として扱われるケースが多いです。所有期間は、税率や申告内容に大きく関わるため、利益か損かは、売却価格と以前の取得費、仲介手数料などの費用をしっかり計算して判断しましょう。
相続登記をすませておく
相続した土地を5年以内に売るなら、まず相続登記をすませておきましょう。
【相続登記とは】
土地の名義を亡くなった方から自分に変える手続き
この登記が終わっていないと、正式に所有者と認められず、買い手が見つかってもスムーズに契約できません。
2024年4月からは相続登記が義務となり、3年以内に手続きしないと過料が科される可能性もあります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
引用:東京法務局「相続登記が義務化されました」
登記は司法書士に依頼するのが一般的で、費用は5万~10万円程度が目安です。後回しにすると売却のタイミングを逃す恐れがあるため、早めの準備を心がけましょう。
特例の対象になるか調べる
相続した土地を5年以内に売るなら、まず使える特例があるか調べましょう。
たとえば「相続空き家の3,000万円特別控除」は、一定の条件を満たせば利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。
これは被相続人が一人で住んでいた古い家と、その敷地をセットで売却する場合に使える可能性があります。築年や相続後に誰も住んでいなかったかなど、細かい条件が決まっています。
申請には市区町村から「確認書」を取得しましょう。土地のみの売却では対象外になるため、建物が残っているうちに制度の適用可否を確認してください。
税負担を減らすために、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
相続した土地の売却は不動産会社・税理士どちらに相談すべき?
相続した土地を5年以内に売るなら、不動産会社と税理士の両方に相談しましょう。
不動産会社は土地の相場や売り方をアドバイスしてくれ、買い手探しのサポートもしてくれます。
税理士は、売却時の税金や控除の使い方など、お金の面で頼りになります。たとえば、家屋付きの土地であれば「相続空き家の特例」が使える場合もありますが、対象条件が細かく、売る前の確認が大切です。




売却時期によって税率も変わるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
相続した土地の売却に関するよくある質問
相続した土地の売却に関するよくある質問をご紹介します。
相続不動産に関する疑問を参考にしてみましょう。
- 兄弟と共有名義でも売れる?
- 築古の空き家は解体すべき?
- 不動産会社の選び方のコツは?
Q:兄弟と共有名義でも売れる?
A:兄弟全員の同意があれば売却できます。
たとえば兄弟3人で持っている場合、1人だけで売ることはできません。売買契約には全員の署名が必要です。誰か1人でも反対すれば売却は進まず、話し合いが長引くこともあります。




スムーズに進めたい場合は、事前に分け方の希望を確認し、意見が合わないときは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
共有名義の土地は「誰と一緒に持っているか」を意識し、しっかり準備することが売却成功のカギになります。
Q:築古の空き家は解体すべき?
A:築年数が40年以上の古い空き家は、売却前に解体を検討する価値があります。
特に、修繕されていない場合、建物付きでは買い手が見つかりにくくなることがあります。再建築できる土地なら、更地にしたほうがスムーズに売れる場合もあります。
買主が「古い家を壊すお金がかかる」と考え、価格を下げてほしいと交渉してくることがあるため、あらかじめ更地にしておくと対応しやすくなります。
ただし、建物があると土地の固定資産税が軽くなる特例が受けられる地域もあるため注意しましょう。解体費用は100万~200万円ほどかかるため、売却前に不動産会社に相談し、更地と空き家付きの査定を比較して判断しましょう。
Q:不動産会社の選び方のコツは?
A:相続不動産の売却経験があるかどうかが重要です。
過去にどんな物件を売ったかを見せてもらえると安心でき、査定のときに「なぜこの価格になるのか」を丁寧に説明してくれる会社は信頼しやすいでしょう。
また、地域の情報に詳しい会社なら、その土地の魅力を活かした提案が期待できます。3社以上に相談し、説明のわかりやすさや対応の丁寧さも比べながら選びましょう。
焦らず、相性を見極めることが成功のカギです。
まとめ:相続した土地の売却方法を理解して適切な方法で売却しよう!
相続した土地を売るには、名義変更が必要です。名義人が被相続人(亡くなった人)のままだと買主に所有権移転登記ができないため、実質的に売却できません。
まずは名義人を自分に変更し、適切な手順で売却しましょう。また、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などさまざまな税金もかかるため、事前に理解しておくことが大切です。
一般的な不動産売却よりも複雑なため、不動産会社や税理士などの専門家に相談しながら落ち着いて売却活動を進めましょう。
「相続」に関する記事一覧はこちら!