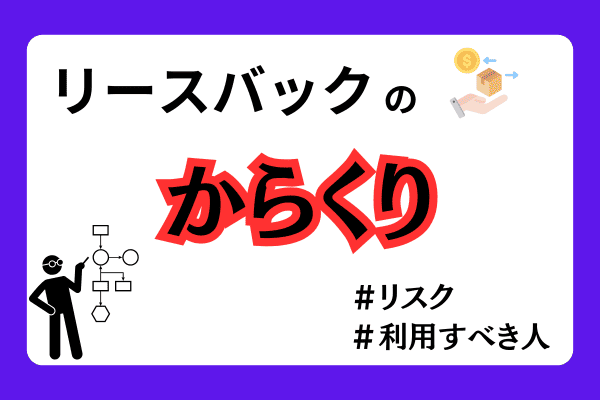- リースバックってなに?
- 利用しても損しない?
- リースバックのからくりを知りたい!
リースバックとは、住んでいる自宅を不動産会社へ売却した後に、賃貸物件として住み続ける方法です。
この記事では、リースバックの仕組みやメリット、からくりなどを詳しく解説します。
【こんな人に読んでほしい】
- まとまった資金が欲しい人
- 資金を調達しつつ今の家に住み続けたい人
- リースバックを利用すべきか悩んでいる人
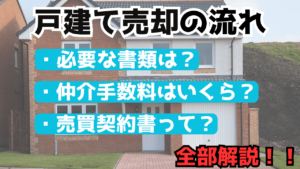
リースバックのからくりとは?仕組みをやさしく解説
リースバックのからくりについて、仕組みや利用の流れを解説します。
リースバックとはどんな制度なのか理解しておきましょう。
自宅を売った後に賃貸物件として住む
リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却した後も、賃貸契約を結ぶことで住み続けられる方法です。
売却により、まとまった資金を得られるため、急な出費や住宅ローンの返済に困っている場合に役立ちます。




ただし、売却後に必ず住めるとは限らず、賃貸契約を成立させる必要があります。また、売却価格は市場価格より低くなることが多いため、内容をよく確認してから利用しましょう。
リースバックの流れ
リースバックを利用する際は以下の流れで進めます。
- 問い合わせ・仮査定の依頼
- 現地調査と本査定
- 契約条件の確認と調整
- 契約の締結
- 売却代金の受け取りと家賃の支払い開始
まず、リースバック専門会社に連絡し、自宅の情報を伝えて簡易査定を受けましょう。
金額に納得すれば、担当者が訪問して詳しく査定します。その結果をもとに正式な買取価格と家賃が提示されます。
条件に納得できれば、売買契約と賃貸契約を結びます。売却後は家賃を払いながら、同じ家に住み続けられます。




リースバックのメリット
リースバックには以下のメリットがあります。
- 自宅を売却しても住み続けられる
- 固定資産税などの負担が軽減される
- まとまった資金を短期間で調達できる
自宅を売却しても住み続けられる
リースバックは、自宅を売却しても住み続けられる方法として注目されています。
例えば、住宅ローンの返済が苦しくなった場合、家を売却し、その後は買主と賃貸契約を結ぶことで引っ越しせずに生活を続けられます。
住み慣れた家で暮らしながら資金を得られるため、高齢者の老後資金対策としても利用されています。
ただし、賃貸契約の条件によっては住み続けられないこともあるので事前に確認しましょう。
固定資産税などの負担が軽減される
自宅を持っていると毎年税金がかかりますが、リースバックにより家の名義が買主に変わるため、今後の税金は支払わなくてよくなります。
例えば、固定資産税が年間10万円かかっていた場合、その支出がなくなります。




ただし、売った年の分は月割りで分けて支払うのが一般的です。
このように、税金や維持費の心配を減らしながら、住み慣れた家にそのまま住み続けられるのがリースバックの魅力です。
まとまった資金を短期間で調達できる
リースバックを利用すれば、自宅を売っても賃貸契約を結ぶことで住み続けられる場合が多く、短期間でまとまった資金を得られます。
通常の売却では買い手を探す時間がかかりますが、リースバックなら不動産会社などが買い取るため、売却活動が不要で早く現金化できます。




医療費や教育費など急な出費が必要なとき、早急な資金調達手段として役立ちます。
ただし、売却価格は相場より低くなる傾向があるため、慎重に検討しましょう。
リースバックのデメリット
リースバックには以下のデメリットがあります。
- 家賃の負担が発生する
- 所有権を失う
メリットと併せて確認しておきましょう。
家賃の負担が発生する
リースバックを利用すると、これまでなかった家賃の支払いが発生します。
自宅を売って資金を得たあとも住み続けられますが、賃貸借契約を結ぶため、毎月の家賃が必要です。
この家賃は周辺相場より高くなることが多く、たとえば売却価格が3,000万円なら月25万円ほどになる場合もあります。




長く住み続けると支出が増え、家計に負担がかかるおそれがあります。契約内容によっては将来の家賃が上がったり更新時の条件が変わったりすることもあるため、事前に確認し、無理なく払えるかよく考えましょう。
所有権を失う
リースバックを利用すると自宅の所有権が買主に移り、自分の資産ではなくなります。所有権を失うことで以下のようなデメリットがあります。
- 家を相続させられない
- リフォームや増改築を自由にできなくなる
- 退去させられる可能性がある
家の所有権がないため、家を相続させるなどの行為ができなくなります。また、リフォームや増改築も所有者の許可が必要になり、自由に行えなくなります。
さらに、契約内容によっては一定期間後に退去が必要になる場合もあります。リースバックを検討する際は、家族の希望や将来を考慮することが大切です。




リースバックの「からくり」として注意すべきポイント
リースバックを利用する際は以下の「からくり」を理解しておきましょう。
- 売却価格が相場より安くなることが多い
- 家賃が高めに設定されることが多い
- 再購入できるとは限らない
- 契約期間が短い場合がある
- 買主の事情で住めなくなる可能性がある
からくり①:売却価格が相場より安くなることが多い
リースバックを利用する際は、売却価格が相場より安くなる点に注意しましょう。
リースバックでは、買い取った後に貸し出すリスクや将来の価格変動を見越して、買取価格が抑えられます。
一般的に市場価格の60~80%程度になることが多く、たとえば2,000万円の家でも1,200万~1,600万円になる可能性があります。
安くなる理由を理解した上で、慎重に検討しましょう。
からくり②:家賃が高めに設定されることが多い
リースバックでは、家賃が周辺の賃貸より高くなることがあります。
これは、売却価格に対して投資家が得たい利益を考えて家賃が決まるためです。
例えば、1,000万円で売却し利益を年10%見込むと、年間家賃は約100万円、月8万3,000円になります。
ローンの残りが多いと売却価格を高めに設定する必要があり、その分家賃も上がりやすくなります。仕組みを理解して慎重に検討しましょう。
からくり③:再購入できるとは限らない
リースバックでは「将来また家を買い戻せる」と思いがちですが、必ずしも再購入できるとは限りません。
契約に条件が書かれていないと、後で希望しても断られることがあります。買い戻し価格が高くなる場合や家が第三者に売られてしまう可能性もあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、再購入の条件を事前にしっかり決めて、契約書に明記しておきましょう。
からくり④:契約期間が短い場合がある
リースバックでは契約期間が短い場合があるため注意しましょう。
そもそも、賃貸借契約には、「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があります。
【普通賃貸借契約とは】
契約期間が満了しても借主が希望すれば更新できる契約。
居住の安定性を重視する人向けで、貸主が正当な理由なく解約できない。
【定期賃貸借契約とは】
契約期間満了で終了し、原則更新されない契約。
事前に終了時期が決まっているため、短期利用や転勤者向けに使われる。
リースバックは、2~3年の定期借家契約になるケースが多く、期間満了後に再契約できるとは限りません。
長く住みたい場合は、「普通賃貸借契約」にして、契約前に再契約の可否や契約形態をよく確認しましょう。
からくり⑤:買主の事情で住めなくなる可能性がある
リースバックでは、買主の事情で住み続けられなくなる可能性がある点に注意しましょう。
自宅を売却したあとも賃貸契約で住み続けられますが、物件の所有権は買主に移ります。
しかし、買主が第三者に売却すると、新たな所有者の意向で再契約がされない場合があります。
特に「定期借家契約」の場合、契約満了時に再契約されなければ退去を求められる可能性もあります。




契約内容をよく確認し、リスクを理解した上で利用しましょう。
リースバックはどんな人が利用すべき?
リースバックは以下のような人におすすめです。
- まとまった資金を早急に必要としている人
- 住宅ローンの返済が困難になった人
- 老後の生活資金を確保したい人
- 相続対策を考えている人
- 自宅の維持・管理費用の負担を減らしたい人
まとまった資金を早急に必要としている人
リースバックは、急にまとまった資金が必要な人に向いています。
自宅を売って現金化し、売却後も賃貸として住み続けられるため、引っ越しせずに資金を得られます。例えば、医療費や事業資金が急ぎで必要なときに便利です。
ただし、家は市場価格より安く売れる傾向があり、売却後は家賃が発生します。複数の業者に見積もりを取り、慎重に検討しましょう。
住宅ローンの返済が困難になった人
住宅ローンの返済が難しくなった方には、リースバックの利用が選択肢の一つになります。
家を所有している場合、住宅ローンを完済するまで支払い難のリスクがともないます。
例えば、病気や怪我、リストラなどにより収入が減少しても、リースバックなら家を売却できるので住宅ローン残債をまとめて返済できます。
ただし、売却価格がローン残高を上回ることが必要です。また、売却後は家賃の支払いが必要で、相場より高くなる可能性もあります。事前に無理のない家賃か確認しましょう。
老後の生活資金を確保したい人
老後の生活資金を確保したい方にも、リースバックが選択肢のひとつになります。
自宅を売却して現金を得られるため、老後の生活費や医療費に充てる資金を確保できます。
さらに、所有者ではなくなるため、固定資産税や住宅の修繕費などの負担もなくなり、家計の安定につながります。
ただし、リース期間や条件は契約内容によって異なるため、内容をよく確認してから利用しましょう。
相続対策を考えている人
相続対策を考えている人にも向いています。
家を売って現金にすることで、相続のときに兄弟で公平に分けやすくなり、争いを防ぎやすくなります。
さらに、売却後も賃貸契約を結ぶことで、今の家に住み続けられる可能性があります。生活環境を変えずに対策を進められるのは大きな安心です。
ただし、家賃の支払いが続くため、将来の資金計画を立ててから利用しましょう。
自宅の維持・管理費用の負担を減らしたい人
自宅の維持費や管理費の負担を減らしたい人にも向いています。
リースバックを活用することで自宅を売却し、そのまま賃貸として住み続けられるため、固定資産税や都市計画税を支払う必要がなくなります。
また、戸建ての外壁や屋根などの大がかりな修理は、所有者が負担する契約になることが多いため、大きな出費を避けられる可能性があります。
マンションでも管理費や修繕積立金を直接払うことはなくなりますが、代わりに賃料や共益費に含まれることがあるため、事前に確認しておきましょう。
リースバックに関するよくある質問
リースバックに関するよくある質問をご紹介します。リースバックに関しての疑問や不安を参考にしてみましょう。
- リースバックは何年住めますか?
- リースバックで家賃が払えないとどうなりますか?
- ローンが残っていてもリースバックできますか?
Q:リースバックは何年住めますか?
A:リースバックで何年住めるかは契約の種類によって変わります。
多くの場合は「定期借家契約」が使われ、2〜3年の契約が一般的です。
この契約は更新ができず、住み続けるには再契約が必要ですが、必ず再契約できるとは限りません。
一方で「普通借家契約」なら更新ができ、長く住める可能性があります。
ただし、リースバックでは普通借家契約が選ばれることはほとんどありません。長く住みたい方は、契約前に再契約の可否や契約内容をしっかり確認しましょう。
Q:リースバックで家賃が払えないとどうなりますか?
A:リースバックで家賃の支払いができなくなると、最終的には退去を求められる可能性があります。
まず、支払いが遅れると貸主から連絡がきます。この時点で早めに相談し、支払う意思を伝えることが大切です。
対応しないと、保証人や家賃保証会社に連絡がいき、代わりに支払われる場合もあります。
それでも支払いがないと書面で正式な督促が届き、家賃が払えないままだと契約が解除されることになります。
最終的には退去を求められる流れになるため、早めの対応を心がけましょう。
Q:ローンが残っていてもリースバックできますか?
A:住宅ローンが残っていても、条件を満たせばリースバックを利用できます。
ポイントは、家を売ったお金でローンをすべて返せるかどうかです。
例えば、ローン残高が1,000万円で売却価格が1,500万円なら、ローンを完済し、残ったお金を手元に残せます。
ただし、売却価格がローンより少ない「オーバーローン」の場合は注意が必要です。
不足分を自分で用意するか、金融機関と相談して任意売却を検討しましょう。任意売却後にリースバックを認めない金融機関もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ:リースバックのからくりを理解して活用しよう!
リースバックの仕組みやメリット、利用に向いている人などを解説しました。
リースバックは、自宅を売却した後も賃貸借契約として住み続けられる方法です。売却によりまとまった資金を得られるだけでなく、愛着のある家に住み続けられるのが特徴です。
また、家の所有者ではなくなり、固定資産税などの税金の支払いも不要になるため、税金の負担を軽減できます。
ただし、家賃の支払いが発生したり、売却価格が安く見積もられる可能性があるため、利用前に仕組みを理解することが大切です。
リースバックは、上手く活用することで、まとまった資金を調達しながら今の家に住み続けられる魅力的な制度です。
利用を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして不動産会社へ相談してみましょう!
「リースバック」に関する記事一覧はこちら!